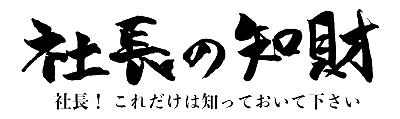特許を取得して法的な権利を確保
ところが大きな設備投資をしたところ…
特許権は、発明者の知的財産を守ってくれます。これは、中小の開発型企業にとっては大手企業に対抗する有効な手段です。
健康食品の開発型メーカーであるC社は、社長が大手バイオ系企業の出身ということもあり、研究開発に非常に力を入れています。また、研究開発の成果を法的に保護するためには、特許が必要だということも十分認識していました。
C社は、新しい研究成果が出るたびに先行技術を調査し、他社が出願していない発明について全て特許出願していました。そして、ある日画期的な発明がなされ、C社の社長は「これは、この会社が大きく飛躍する大チャンスだ!」と、早速特許出願を行い、新たな工場を建設することも決定しました。
無事特許を取得し、工場も完成し、生産ラインが稼働し始めました。ところが新しい効能があるにも関わらず、新商品が全く売れないのです。市場にある既存の商品にはない性能に自信を持っていたC社の社長は、そこでようやくマーケティングの重要性に気づきました。新商品をヒットさせるためには、ネーミングや箱のデザイン、宣伝広告、流通など、製品本体以外の要素も重要だということを実感した時には、既に大きな負債を抱えた後でした。
このように特許を取得しても、商品が売れないケースは世の中に数多くあります。重要なのは、本当に出願する価値がある発明かどうかという視点を持つことと、その発明を特許権で法的に保護しながら、収益を実現できるマーケティングを実施することです。
自ら発明したものは、発明者にとっては愛着があるため、得てして過大評価してしまう傾向があります。だからこそ、第三者の視点で冷静に分析する必要があるのです。出願すべきかどうかも含めて弁理士に相談することで、無駄な出願に出費することを避け、その後の事業リスクも軽減できます。