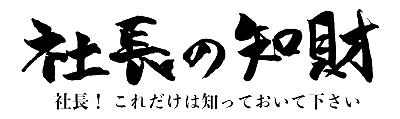社長は、単なる着想をしたに過ぎない。
具体的な装置や仕様に具現化した依頼先の会社の社員が真の発明者
仮想現実と訳されるバーチャルリアリティ(VR)。教育や医療、エンターテイメントの世界で、VRがかなり普及してきています。そのVRを楽しむため、新しい機能を追加した画期的なデバイスの漠然としたアイディアをT社の飯島社長が着想しました。
そして、他の案件でも制作依頼していた協力会社に、その製品化を依頼したのです。と同時に、T社は自社で特許出願を行い、特許権を取得しました。
ところが、その後その制作会社がそのVRデバイスの類似品を製造販売し始めたのです。これに対して飯島社長は侵害訴訟を提起しました。ところが、裁判所は「そのVRデバイスの真の発明者は、協力会社の技術者である」と判断したのです。
今回の事案について弁理士から受けたアドバイスのポイントは、以下の通りです。
「ユニークなアイディアを思いついても、自社で開発できないケースは結構あります。そういった場合、外部の協力会社に制作や開発を依頼することが多々あります。
今回のように、社長はコンセプトや大まかな発想を考えたとしても、“こういう機能が欲しい”という願望・要望を協力会社に伝えただけであって、それを実現するための具体的な手段(仕様・方法等)を考えだしていないので、発明者とはなり得ません。それを実現するための具体的な手段(仕様・方法等)を考えたその協力会社の社員が発明者となり得ます。そして、特許出願することができるのは「特許を受ける権利」を有する者だけであり、原則として発明者に特許を受ける権利が帰属します。したがって、発明者以外の者が特許出願するためには、原則として特許を受ける権利を譲り受ける必要があります。特許を受ける権利を有さない者が特許出願し得られた特許は、本来権利者になり得る者から無効審判を請求されれば無効になります。
外部の会社に依頼する場合、成果物の特許出願はどちらが行うのか、共同で行うのかについて、きちんと契約書面で締結しておくことが重要です。」